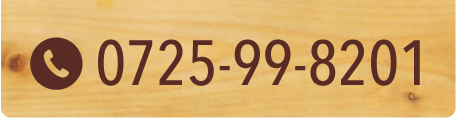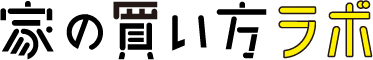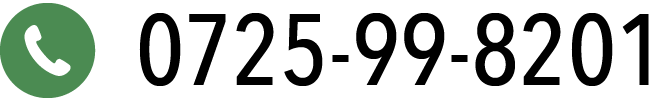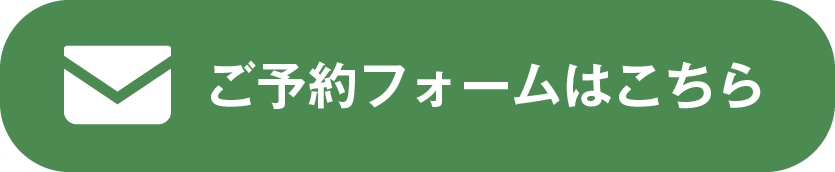こんにちは。ファイナンシャル プランナーの森次です。
2020年ぐらいから金融庁は急激に金融教育に舵をきり始めました。
その大きな理由としては、本格的な物価上昇時代に入り、貯蓄から投資へシフトしていかないと預貯金は目減りしていき、老後の年金生活だけでは困ってしまうからです。
その中でしきりに使われている言葉が「資産形成」です。
昨今よく使われている資産形成とは具体的にどのようなものなのでしょうか?
金融庁がお勧めする資産形成に必要な3ステップは、
①家計の見直し(余剰資金の確保)
②ライフプラン(目的の明確化と人生設計)
③マネープラン(長期分散積立投資)です。
家計の見直し
ついつい今流行りだからとか、損したくない、置いて行かれたくないという理由で、焦ってとりあえずNISAやiDeCoを始めましたという人が多いのですが、この考え方はとても危険です。
なぜなら投資は長期間しっかりと資産を成長させていく行為であり、短期で売却するとリスクが大きくなるからです。
だからまず、家計のお金の流れを把握する必要があります。
収入から固定費を引いて、変動費も引いて、その上で年間として余っているお金(余剰資金)がいくらぐらいあるのかを確認してください。
家計のお金(収入)を「使う」と「貯める」と「増やす」という3つの支出に色分けする必要があります。
もちろん生活をより良いものにするのが「使う」ですから、自分たちがどのような人生を送りたいのかという想いを一番反映させたいところです。
ただ、すべてを使ってしまっては、どこか不安で心から楽しんだ人生を送れなかったり、今使うということに100%の許可を出せなくて疑心暗鬼になってしまいます。
だから未来への仕送り「増やす」が必要なのです。
ただ、増やすには時間が必要なので、様々な予期せぬ環境の変化にも耐えうるだけの余剰資金を「貯める」必要があります。
一般的には生活費の3~6か月分と言われていますが、逆に言えばそれ以上貯めても、物価上昇に負けてしまいもったいなく感じるかもしれません。
また、「貯める」や「増やす」ばかりにとらわれ、今を楽しめなかったら意味がありません。
ということで、まずは、家計を把握し、必要であれば、「使う」「貯める」「増やす」のバランスを見直していく必要があります。
ここで創り出せた余剰資金が投資の原資にもなります。
ライフプラン
次に必要なのがライフプランです。
いわば人生を大航海に例えたら、海図のようなイメージです。
地図があるから、現在地と目的地までの距離がわかったり方向がわかったりし、より最適な乗り物や準備がわかります。
未来までのお金の見える化をするのがライフプランですので、自分たちがどれだけ何にお金と時間を使って、これから生きていきたいのかの優先順位を考え、自分たちで選択した後悔のない未来を手に入れられます。
また、わからないものに人は恐怖を抱きます。
やみくもに未来を不安に思うのではなく、ちゃんと見える化し向き合うことで、何が問題なのかを考え、対策を考えることもできます。
ただやみくもに金融商品に加入してみたが不安が消えないという人は、ライフプランによる見える化ができておらず、何が問題で、その問題をどの金融商品がどのように解決してくれるのがわかっていないからです。
ここまでの家計の見直しとライフプランは、お金の健康診断のようなものです。身体を定期的に調べるからこそ、問題を事前に把握し対策を打てるのです。金融商品の処方はそのあとなのです。
マネープラン
最後がいよいよ資産運用や投資などのマネープラン(お金の使い方)です。
具体的に問題解決に向けた、または自身のニーズに沿った金融商品などを使い、資産を形成していくのです。
大きく言うと、金融業とは「銀行」「保険」「証券」です。
人から預かったお金を運用し、預けてくれた人に還元する方法がこの3社は違います。振り込みやATMといった流動性というサービスを提供するのが銀行。
万が一の時の保障を確保してくれるのが保険。
資産運用し、お金を増やしてくれるのが証券です。
この資産運用に関して金融庁は、「長期分散積立投資」という手法を推奨しています。
短期で売買せず「長期」で保有し、投資信託を使って「分散」することで長期間ほったらかしにしても紙切れになるリスクを極限まで抑え、「積立投資」で日々の株価の乱高下に一喜一憂せず、安心して投資を続けられる仕組みです。
まとめ
1.家計の中のお金を把握することで、余剰資金を確保し、無理のないお金を原資にする。
2.ライフプランに基づいた目的地を明確にし、解決しなければいけない問題や自身の優先順位に基づいた資金計画を立てる。
3.短期(銀行)、長期(証券)、万が一(保険)を活用し、目的に沿った金融商品を選び、長期間ほったらかしにしても安心して資産形成できる仕組みを取り入れる。
この3ステップが金融庁が推奨する資産形成の具体的な方法です。
ぜひ参考にしてください。